過去問は何年分前までするべき?大学受験の赤本の使い方
2018.10.15

大学の過去問は何年分まで遡ってしたらいいのでしょうか?平均的には、このくらいの過去問を解いているようです。
しかし、過去問の使い方は大学受験の勉強の仕方によって違いがあることが多いので、自分の勉強のパターンやスケジュールと照らし合わせて考えるといいでしょう。
大学の過去問を解くときのポイントや赤本の使い方について紹介します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
受験勉強のやる気が出ない人へ!試してほしい方法を紹介します!
受験勉強をしなくてはいけないのに、なかなかやる気が出ない。 と、お悩みの受験生はいませんか? ...
-

-
高校のテストでの赤点は何点?赤点の基準と留年・欠点・青点とは
高校のテストでの赤点の基準が知りたいという人もいますよね。テストで赤点を採ってしまったら、この先の自...
-
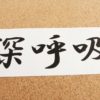
-
受験直前の不安対策!アナタだけじゃない!誰でも不安を感じます
受験直前に不安な気持ちに襲われて、頭が真っ白になったり、焦ったり落ち込んだりするのは、みんな同じです...
-

-
部活の後の勉強は眠い!部活と勉強を両立する方法と眠気の対処法
部活でたくさん運動をして、家に帰ってきてから勉強をすると、どうしても睡魔に襲われてしまう瞬間がありま...
-

-
大学へ行きたい!社会人から大学へ進学を考える方へのアドバイス
一度社会に出てから、やっぱりもう少し勉強したいとか、キャリアを上げるために大卒の資格が欲しい場合など...
-

-
テスト勉強全然してない!これはさすがに間に合わないな、時には
テスト勉強ってやろうやろうと思っていても、なかなか取りかかれないものなんだよね。 そんなふうに...
スポンサーリンク
この記事の目次
大学の過去問は何年分取り組めばいい?
高校生ともなると、大学受験を意識し、過去問を何年分解ければ、合格に繋がるのだろう?と悩む時期に入ると思います。
そこで、ここで何年間分の過去問に取り組んでおけば良いのか、対策をみていきましょう。
「5年分の過去問に取り組んで、出題傾向を見る」
進みたい大学の出題傾向を把握するには、ある程度の分量の過去問を解いて、傾向を知る必要があります。
一般的には5年分の過去問を解いて、2回以上間違えた場合ですが、教科書などを復習して、基本を復習し、過去問がスムーズに解けるまで繰り返したようです。
本番で実力を発揮するには、過去問を解いて、自分にあった戦略方法を立てることにあるようです。余裕をもって、過去問に取り組むことができると、受験で有利なのではないでしょうか。
大学の過去問は何年分か解いてみると傾向がわかる!
大学の過去問ですが、5年以上遡って解いていくと、出題傾向がわかり、入試本番までに、自分なりの対策がとれることがわかりましたよね。
入試本番まで、自分が行きたい大学の過去問を解いていく、そうしていく内に、その大学の出題傾向というものがわかってきますよね。
例えば、どういう傾向がわかるかというと、数学だと「OOとXXの応用問題が出てきている」であったり、英語は「英作文に特徴がある」など、その大学が出題する傾向のようなものが見えてくると思います。その大学の色を把握して、その大学の入試に合わせた勉強法をしていくのです。
その大学の色であったり、傾向を知っているだけでも、入試対策に繋がると思います。
ただ、それだけに集中するのもよくはありません。大学で出題されやすい部分だけではなく、他の部分の勉強もしていきましょう。
大学の過去問は何年分から始める?古いほうから?
大学の過去問を解いておいた方が、その大学が出題する傾向がわかり、入試に向けて充分な準備ができることを、上記ではみてきましたよね。
大学の過去問を解いておいた方が、入試対策になることはわかった。でも、その過去問、古いほうから始めた方が良いのか?疑問に思いませんか?
答えからいうと、それに対する正しい答えはないようです。
「古いものからやっていた方が良い」という意見もあれば、「新しいものからやった方が、自分が受ける時の状態に近いものである」という意見もあります。
そうすると、何が正しい答えか、になってくると思いますが、「人それぞれ」というのが答えになってくると思います。
また、「自分にどれだけ時間が残されているのか」それも意識して取り組むべきだと思います。判断基準は、人それぞれ、異なっていくのではないでしょうか。自分に合う方法を選ぶべきです。
大学の過去問に取り掛かるのはいつから?
大学の過去問ですが、古い方から解いた方が良いのか、または最新のものから解いた方が良いのか、それは人それぞれが判断し、自分に残された時間も関連してくることを上記ではみてきましたよね。
その過去問ですが、いつぐらいから解き始めるのでしょうか?
- 9月までに解いていた 約5割
- 8月までに解いていた 約4割
上記が目安になってくると思いますが、志望大学が決まっているのなら、なるべく早い内に、過去問を解いておき、入試の傾向を知っておくことが鍵になってきます。
時間が中々なかった!と言う人でも、過去問を一度やってみることをお勧めします。
志望校に高得点で合格したい、そう思うなら、過去問をとくことが近道だというのが、ある方の意見です。
そして、志望校の問題が解けるようになってきたら、普通の学校のテストも解けるようになってくるのでは?というアドバイスもあります。大学の過去問、是非解けるようにしておきたいですね。
大学の過去問を解く時のポイント
大学の過去問ですが、先輩方々は8、9月には解いていたこと、また大学の過去問を解けるようになったら、普通の問題も解けるようになるというアドバイスを上記ではみてきましたよね。
最後に、折角大学の過去問をこれから取り組むのでしたら、解く際のポイントとなるものを抑えて、より効果的に勉強ができる方法を紹介したいと思います。
- 時間を計る
過去問を解く際に、時間を計っていきましょう。 - 苦手な問題は遡って解く
過去問を解いていくうちに、得意な問題と不得意な問題が出てくると思います。
不得意な問題に関しては、大問を解いていくと、苦手分野の克服にも繋がります。 - 記述問題は先生にみてもらう
和訳や英作文の問題ですが、自分の答えを、先生に添削してもらいましょう。 - 何回か解く
復習をすること、また何回か解いていくうちに、似たような問題が出てきても、解くことができます。









