知っておきたい豆知識!失業保険を受給するには6ヶ月の加入条件
2018.4.23
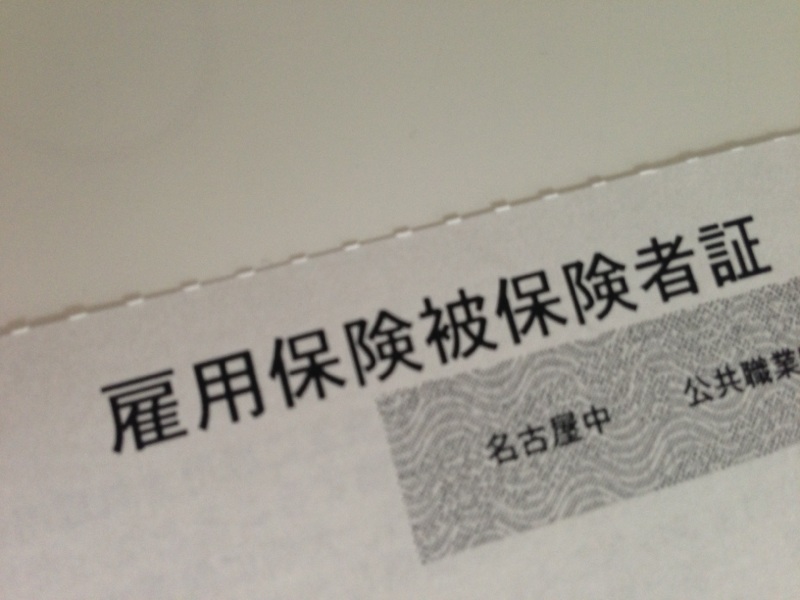
失業保険を受給するには、雇用保険を6ヶ月加入していることが条件となります。
初めて受給される方にとっては、戸惑うこともありますが、必要な知識として知っておくと焦らずにすみますよね。それにはどんな条件があるのでしょうか?
今回ここでは、雇用保険を受給する際のお役立ち情報について調べまとめてみましたので、是非参考にしてみてください。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
住民票を移動しなければならない理由とは?デメリットをご紹介!
引越しをすると必ず、住民票を新しい住所に移動しなければならないと言う理由がありますが、もししなければ...
-

-
友達から結婚の報告なしの場合は?結婚報告のタイミングはいつ?
あなたは友達へ結婚の報告はどのようにしていますか?直接会って報告したり、電話、メール、LINEなどの...
-

-
中央線が黄色の場合は追い越し禁止!交通ルールを守って安全運転
自動車の運転免許証をお持ちの方であれば、自動車教習所で習ったことだと思いますが、道路にはセンターライ...
-

-
義父の葬儀で忌引き休暇を取る時に日数は?マナーや注意点を解説
義父の葬儀で忌引き休暇を取ることになったとき、一体自分は何日の休暇を取ることができるのかわからないこ...
スポンサーリンク
この記事の目次
失業保険をもらうには、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月が条件となる。
会社を辞めてもすぐに就職先が決まらない場合もありますよね。
そんな時、失業期間中の生活を心配しないで送ることができるためにもらうのが、失業保険です。
この保険は、生活を心配せずにいち早く仕事を見つけて再就職してもらうために支給されます。
失業保険をもらうためには条件が二つあります。
一つ目は、退職した日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が1年以上ある場合。
二つ目は、退職した日から以前に1ヶ月ごと区切った場合、賃金の支払いがあった日が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合。
この二つを満たしている場合は失業保険をもらえる資格があります。
しかし例外もあります。それは会社都合で退職した場合です。
1つ目は、退職した日より前の一年間に雇用保険に6ヶ月以上加入していた場合。
二つ目は、退職した日から以前に1ヵ月ごと区切った場合、賃金の支払いがあった日が11日以上ある月が6ヶ月以上ある場合です。
要するに12ヶ月以上、働いていれば大丈夫なのです。
受給期間はひとつでなくてもかまいません。数社合計して12ヶ月以上努めていれば大丈夫です。
給与明細に雇用保険料という欄があれば雇用保険に加入していることになります。
雇用保険はすべての事業所が加入しなければならないのですが、加入していない会社もまれに存在します。アルバイトの場合は加入していない場合もあるので確認が必要でしょう。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえる条件って本当?
実際失業保険は、12ヶ月働かなくてはもらえません。
そしてすべての月において11日以上働いていることが条件です。
12ヶ月以上勤務しているときは、それ以前の月において11日以上働いている月が存在していれば大丈夫です。
勤続6ヶ月から失業保険をもらえる方を、特定受給資格者といいます。
リストラ、会社都合により会社を辞めざるを得ない場合の方を指します。
また特定理由離職者という方もいます。賃金が下がったり、配偶者が別の土地に異動になった場合、事務所の場所が変わり通うことが難しくなった(片道2時間以上通勤にかかる)など、やむを得ずやめなければいけない理由により退職した方を指します。
この場合も勤続6ヶ月から失業保険がもらえる場合もあります。
特殊な場合ですので、これはハローワークが判断し決定されることとなります。
失業保険はどのくらい働くと受給することができる?加入期間は6ヶ月が条件
失業保険は12ヶ月働くと受給することができます。
またすべての月において11日以上働いていることが大切です。
失業保険はいくらくらいもらえるのでしょうか?
年齢と給与にもよりますが、5割~7割程度のようです。
自分自身の都合で退職した場合は、失業保険をすぐに受給することはできず、3ヶ月の給付制度期間後になります。
ただし、次の場合はすぐに失業保険をもらうことができます。
会社の都合で退職や解雇になった場合や契約期間満了になって雇用期間が終了し退職した場合などです。
退職日直前の6ヶ月の期間のうち、3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働をした場合は、自己都合でも失業保険をもらえます。
負傷などで、就労が困難となり退職した場合や、定年退職をした場合もこれに該当します。
2日入社の場合は、翌年の同じ月の1日以降に退社しなければ受給資格はありません。
雇用保険被保険者証を見ると正確な資格取得日を確認することができます。
失業保険をもらえる条件をきちんと知っておこう!
失業保険をもうためには、雇用保険に加入していることが必要となります。
雇用保険は、基本すべての事業所が加入しなければならないことになっていますが、パートやアルバイト、派遣社員の場合などでは加入していない場合もあります。
雇用保険適用事業所に雇用されており、31日以上継続して雇用される見込みかどうか、1週間の所定労働時間が20時間以上であるかどうかが雇用保険加入の決め手となります。
この3つの条件に該当していれば、パートやアルバイト、派遣社員でも加入が義務とされています。給与からは原則0.5%が雇用保険料として引かれることになります。
雇用保険に加入していることが失業保険を受給する前提ではありますが、雇用保険に加入している以外にも条件はあります。
退職した日よりさかのぼって2年間のうち雇用保険に加入していた期間が1年以上あること、会社の都合で退職や解雇になった場合は失業した日より前の1年間のうち雇用保険加入期間が6ヶ月以上存在すること、求職の活動をしているかどうか、この3つの条件を満たしていれば、受給資格を得ることができます。
自己都合の失業保険は3ヵ月後の受給となるが、特定理由離職者になると優遇される
自分自身の都合で退職した場合は、失業保険をすぐに受給することはできず、3ヶ月の給付制度期間終了後に受給となります。
自分自身の都合で退職した場合の方を、一般受給資格者と呼ばれます。
しかし、自分自身の都合で退職した場合でも、正当な理由がありそれを政府が認めた場合は、特定理由離職者となります。
特定理由離職者は特別措置を受けることができます。特定理由離職者の正当な理由はいくつかあります。
- 病気などや心身的な不調などで健康状態が悪化し退職した場合。
- 契約期間満了になって雇用期間が終了し退職した場合。(更新の希望が認められなかった場合)
- 両親の介護などにより、働くことが困難になって退職した場合。
- 配偶者や家族と離れて暮らすことが困難になり退職した場合。
- 妊娠や出産、子育てのため退職し、失業保険受給期間を最長三年間延期できる受給期間延期間の延期措置を適用した場合。
- 就業場所の移転により通勤時間が片道2時間以上になるため、通勤困難となって退職した場合。
- 人員削減により、会社が希望退職を募ったので希望し退職した場合。(会社から勧奨があった場合などは適用されない)
上記の場合は優遇措置を受けることができます。上記の理由に当てはまる場合は、ハローワークでその旨を伝えてください。











